-

介護JJはケアマネ正社員の求人に強い!支援金(実体験)や口コミ、登録後から転職決定までレビューするよ!
-



ケアマネでも稼げる副業8選!在宅ワークや副業バイト、スキマ時間で稼ぐ方法とは?
-


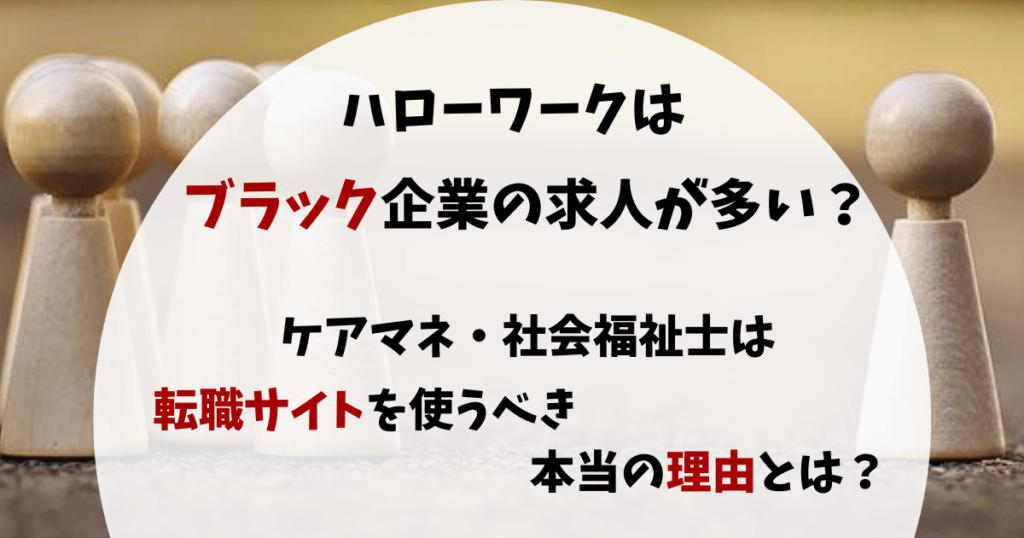
ハローワークの求人はブラック企業が多い?ケアマネ・社会福祉士が転職サイトを使うべき本当の理由
-


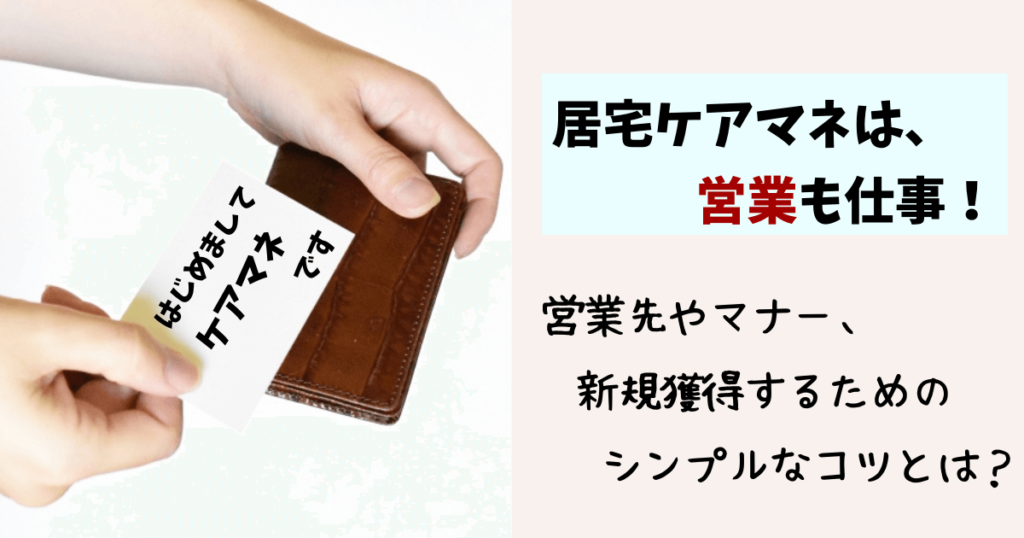
居宅ケアマネは営業も仕事!営業先やマナー、新規獲得のシンプルなコツとは?
-


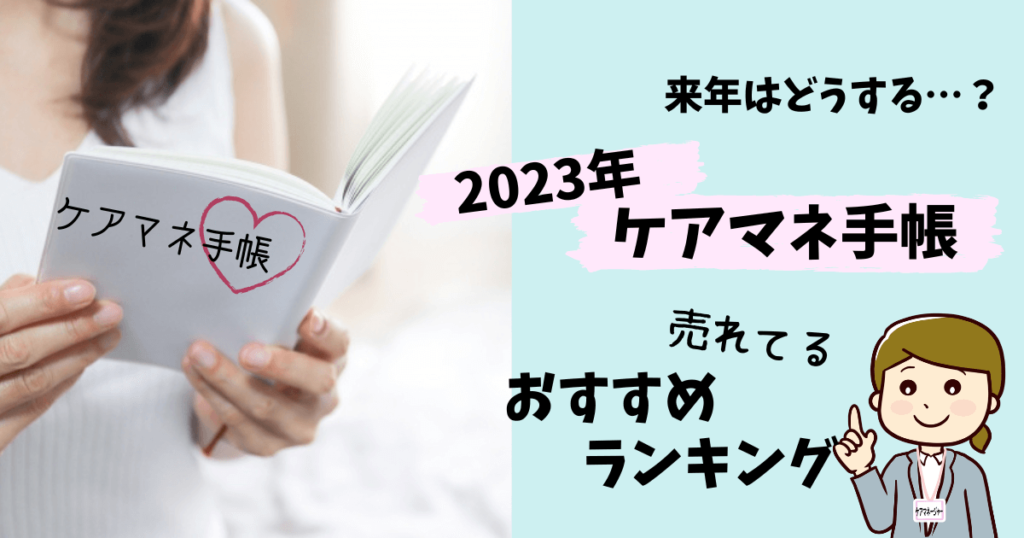
ケアマネ手帳【最新2023】おすすめは?中身をランキングで紹介
-


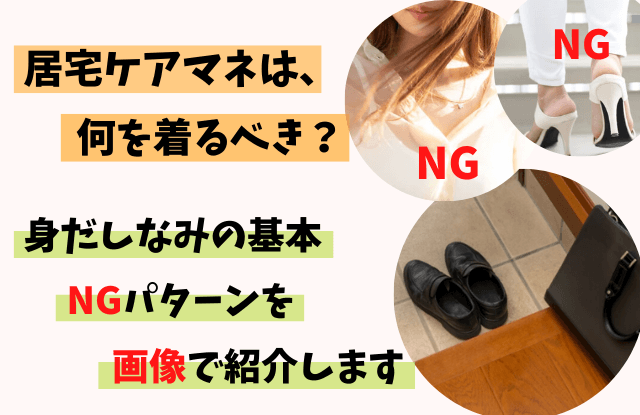
居宅ケアマネの服装は何がベスト?基本やNGな身だしなみも画像で紹介!
居宅ケアマネはノルマがある?ケアマネ職場でノルマがなくならない理由を解説
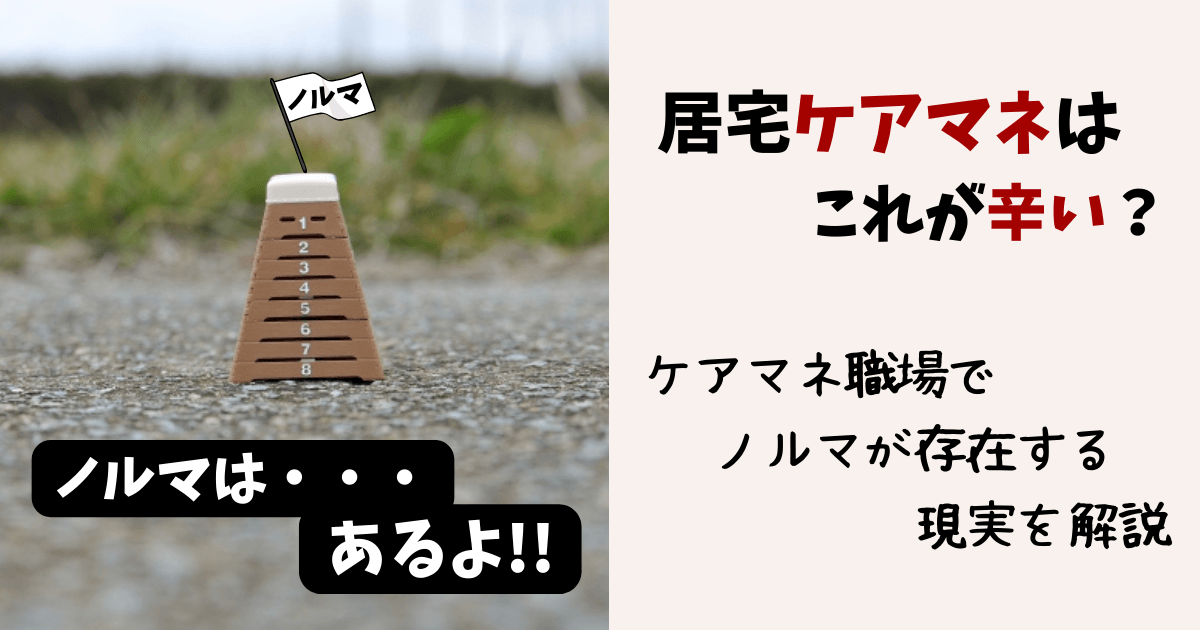
居宅ケアマネって、仕事でノルマはあるのでしょうか。
ノルマと言えば、たとえばコンビニのバイトです。
私も経験者ですが、辛いのはクリスマスシーズン。
「クリスマスケーキを売る」というノルマがあり、「30個売らなきゃ〜」と嘆く先輩もいました。
では、居宅ケアマネはどうでしょう。
私の経験から言うと、居宅ケアマネの職場にノルマはありました。
担当人数のノルマや、サービス調整をするときに自社を使えというノルマ・・・。
新人ケアマネの時には、ノルマが本当に辛かったです。
でもその後は管理者となり、職場全体の事情も見えてきました。
すると、ノルマについて考え方が変わった・・・という経験もしています。
そこで今回は、居宅ケアマネのノルマについて、現場の事実をお伝えします。
居宅ケアマネに転職したいけど、ノルマがあるか不安。
そう思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
【事実】居宅ケアマネの職場にノルマは・・・ある!
先に結論をお伝えすると、居宅ケアマネの職場にはノルマがあります。
ただしケアマネの求人には、「ノルマあり」とは絶対に書かれていません。
今は、「これ、ノルマだから!」と言ってくる上司も少ないでしょう。
ノルマという言葉自体が、自主性やモチベーションを低下させてしまう可能性があるからです。
それに昨今では、「パワハラだ!」と問題になるかもしれません。
一方で、「ノルマなし!自分のペースで働けます!」とアピールしている求人もあります。
でも、それって本当!?って思いませんか?
実際に居宅ケアマネとして働くと、例えば、


担当件数は、35人(介護予防を含め39人)は持ってね
などと、言われることが多いです。
ちなみに私の職場(居宅)では、担当件数は30人が最低ボーダーライン。
ノルマとは表現していないし、達成できないからといって、減給もありません。
(人事評価には関係あるかな・・・)
でも担当件数が30人以下になると、上層部から「この数字で部署は存続できるのか・・・」と圧力がかかります。
これでは、「ノルマだ!」と言われているようなものです。
居宅ケアマネの職場では、このような「ノルマと言わないけど、実はノルマ」なことが存在しているのですね。
【チェック!】居宅ケアマネは営業も仕事!営業先やマナー、新規獲得のシンプルなコツとは?
【体験談】ノルマありの居宅ケアマネは辛い・・・
では実際に居宅ケアマネの職場では、どんなノルマが存在しているのか。
居宅ケアマネ歴9年の私が体験した、「ケアマネのノルマ」エピソードを紹介します。
どれも現実ですよ~!
【チェック!】ケアマネは心が折れる仕事?私が休職するまでの体験をお話しします
【チェック!】ケアマネが「できないこと」とは?業務範囲外でも断れない現実(本音)
【居宅ケアマネのノルマ①】担当件数は30人以上・・・と強制された
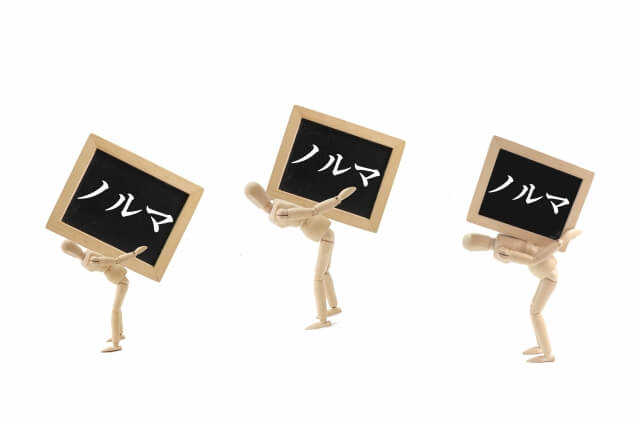
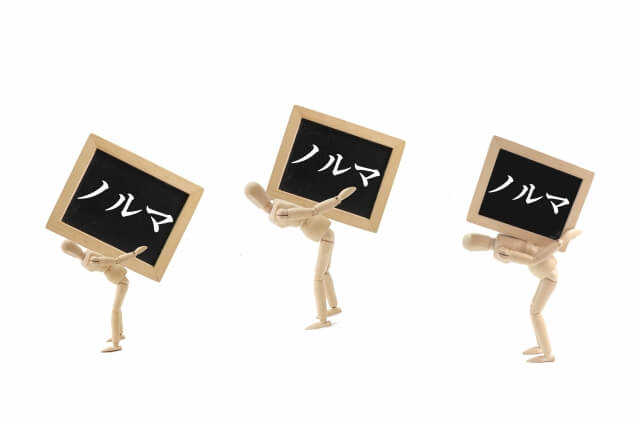
これは私が新人ケアマネで、民間の居宅介護支援事業所にいたころの話です。
社長から、「担当人数は常に30人以上であること」というノルマを課せられました。
担当件数30人を切る月があった時は・・・、チクチクと説教をされます。
毎日何をしているのか手書きで日誌を書かされ、「この日は何をしてたんだ!?」と説明を求められたりもしました。
支援経過を書くことに精一杯なのに、二重に同じことを書かされる苦痛!
心から、無駄な時間だと思っていました。
そしてこれは、10年位前に私の知人ケアマネが体験した話です。
居宅介護支援事業所を経営するのは、介護出身ではない社長。
その社長も、居宅のケアマネに限度ぎりぎりまで担当件数を持つように指示してきたそうです。
「ケアマネの訪問は、佐川急便と一緒でしょ!1日10件は周れるだろ!」
と、暴言を吐かれたとのこと。
現場を知らない社長の理不尽なノルマ。
知人のケアマネは、うんざりして退職しました。
【居宅ケアマネのノルマ②】新規開拓で、毎月営業10件というノルマ
居宅ケアマネは、事業所によっては「営業」もやります!
これも、私が新人ケアマネだったときに辛かったノルマ。
新規利用者を増やすため、医療機関に営業するよう社長からの指示がありました。
それも、営業ノルマとして毎月10件!
ちなみに、本来のケアマネ業務が忙しいという事情はスルーです。
営業計画や報告書を提出し、ノルマを達成しているかチェックされました。
【チェック!】御用聞きケアマネの「言いなりケアプラン」の実例!ケアマネが利用者の言いなりになる現実とは?
【居宅ケアマネのノルマ③】自社の介護サービスを使え!
福祉用具事業所を併設する居宅で、ケアマネをしていた時の話です。
福祉用具の事業所って、得意分野があったり、搬入スピードや融通の利く範囲が全然違います。
品数・スピード・対応全てにおいて、他社の事業所が勝っているとわかっていても・・・。
社長から「うちの事業所を使え!」と言われました。
こっそり他社を使ったりもしましたが、バレて怒られたものです。
つまりこれって、明確なノルマですよね。
ケアマネジメントの中立性って?
利用者のニーズを何だと思っている?
うんざりした気分になりました。
ケアマネの転職先、福祉用具の営業事務ってどう?給料下がっても負担は軽い?【体験談2選】
【居宅ケアマネのノルマ④】不必要なサービス調整
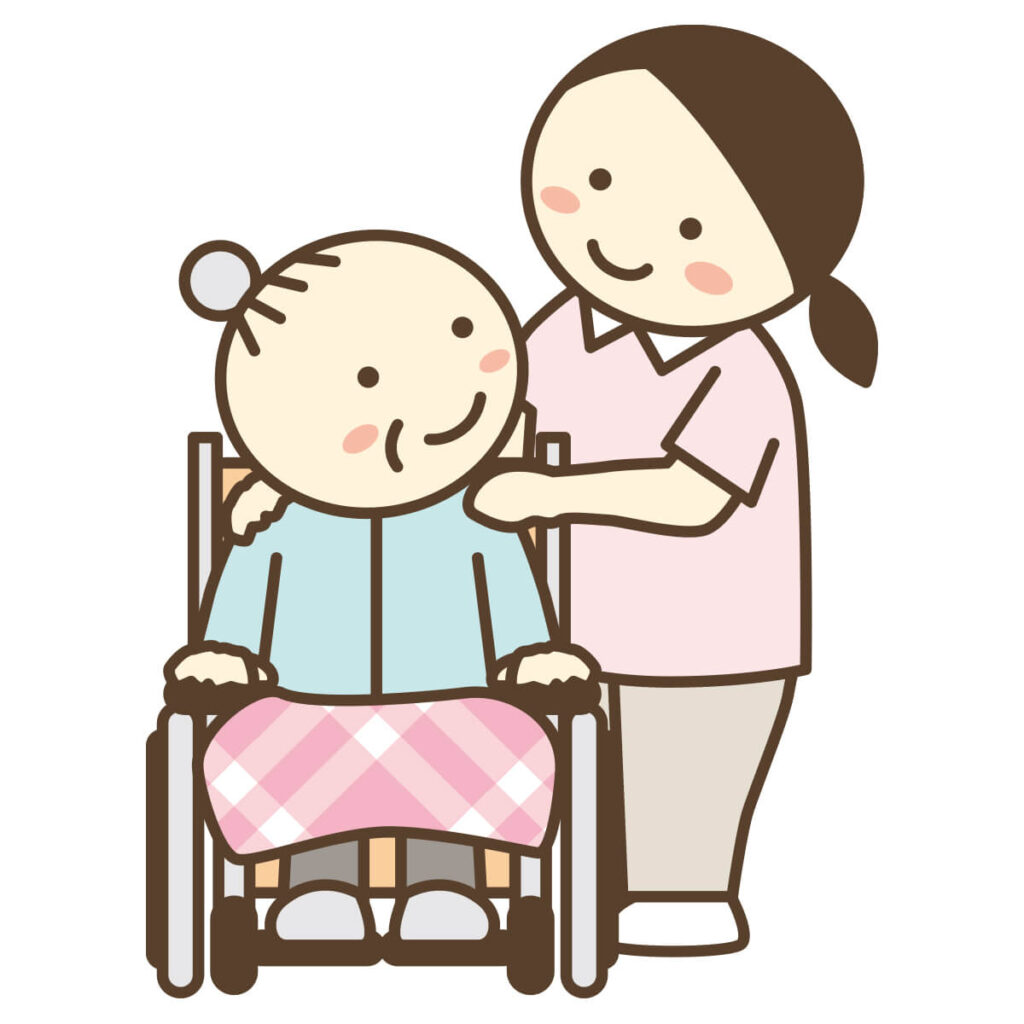
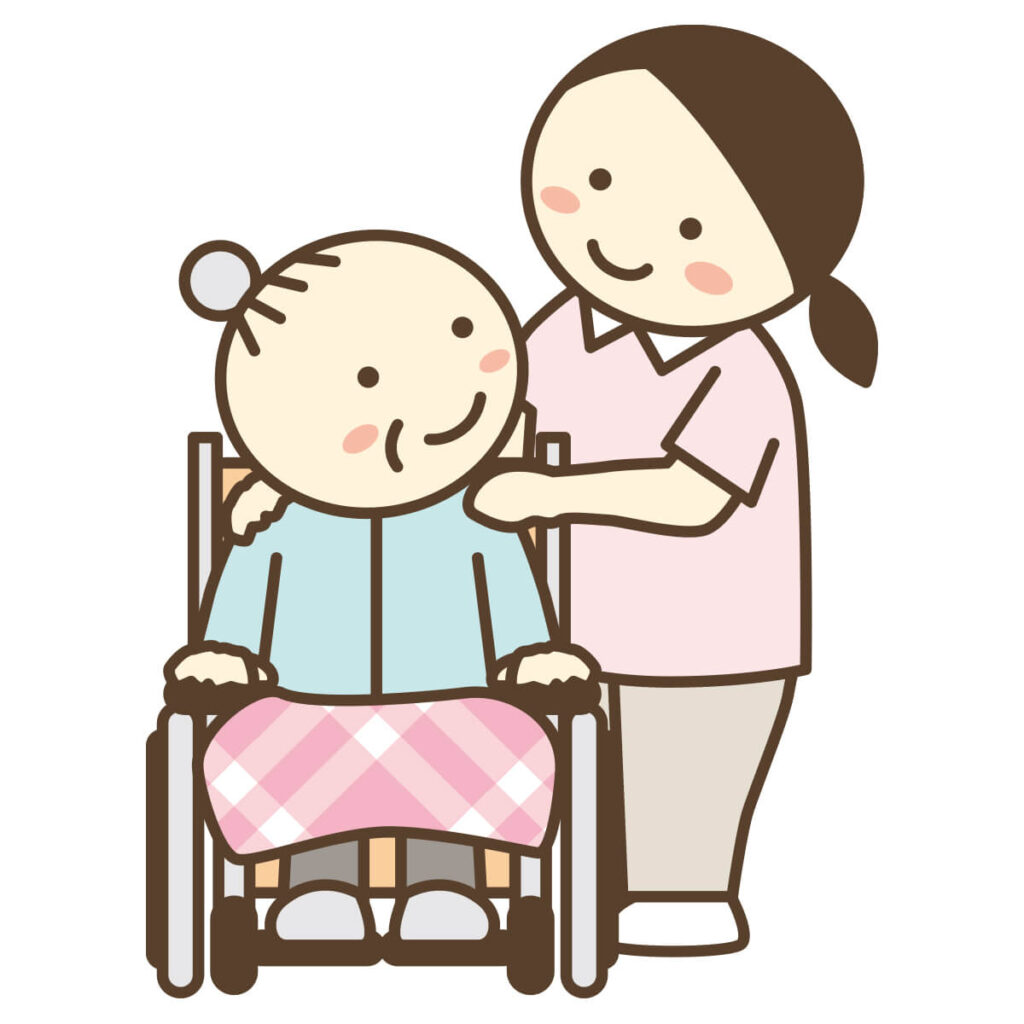
居宅ケアマネのノルマは、職場内部だけの話ではありません。
これは、サービス付高齢者住宅の入居者を担当したときのこと。
その施設は、併設事業所のヘルパーを毎月10000単位は利用することが入居条件でした。
家賃・諸費用が激安の老人ホームは、併設事業所の介護サービス利用がないと利益が出ません。
介護業界の「闇」ってやつですね。
私の担当した利用者さんは、けっこう自分で動けました。
でも・・・。
そのサービス付き高齢者住宅から退去すると、他に行く場所のない方です。
不必要なサービスだとわかっていましたが、渋々ケアプランを作成しました。
これも、居宅ケアマネ業界における「ノルマ」のひとつでしょう。
居宅ケアマネの職場で、なぜノルマが存在するの?
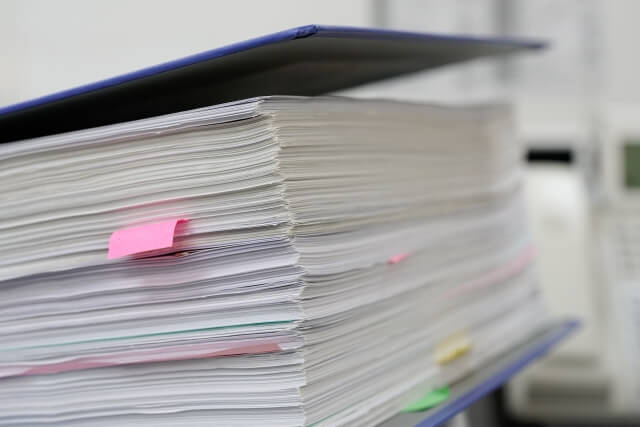
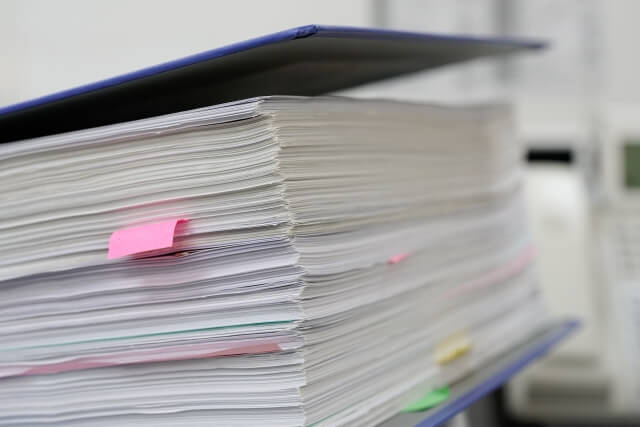
では、なぜ居宅ケアマネにはノルマが存在するのでしょうか。
それはなんと言っても「収益のため」です。
居宅介護支援事業所の収入は、「単価×利用者人数」で計算されます。
なので収益を上げるには、利用者人数を増やすしかありません。
ちなみに居宅介護支援事業所は、単体で黒字経営をするのは難しいのが現実です。
(出来なくはないけど、加算をフルで申請したり、限度まで担当件数を増やさないと厳しい)
そのため、複数事業所の法人では、ケアマネ部署は赤字になりがち。
併設の介護事業所を利用したケアプランで、赤字分を補填していくという考えが一般的です。
つまり、会社経営をしていくには、ノルマは必要な側面もあるのです。
ただ自社の介護サービスばかりで、利用者さんを囲い込む事例も問題になっています。
そこで、特定事業所集中減算や公表制度ができましたが・・・。
減算や返戻ギリギリまで、自社サービスを使えという指示はありました。
ケアマネ経験者でなければ、数字だけで判断をする経営者も少なくないでしょう。
だから、経営者は「担当件数を増やせ」「自社のサービスを使え」とノルマを課してくるのです。


赤字なんだから、目一杯人数を持つのは当然だ!
事務仕事の何がそんなに大変なんだ!
そんな言葉で、叱責されたこともあります。


ケアマネの仕事はイレギュラーなことも多いし、1人の利用者に時間がかかることもある!
居宅ケアマネならではのこんな事情も通用しません。
居宅ケアマネにノルマは必要!?
【居宅ケアマネのノルマ】管理者としての立場


こんな話を聞くと、「ノルマがあるなんて、居宅ケアマネをするのが不安」と思ってしまいますよね。
ここからは、私が管理者に昇進し、ノルマを課す側になったときのことをお伝えします。
中間管理職の立場になってみて、ノルマ(のようなもの)は必要なんだ・・・と感じました。
それはケアマネ部署を存続させて、働いているケアマネの生活を守るためです。
そもそも私は、「ノルマ」という言葉自体が好きではありません。
「やらなくてはいけない」「上からの命令」というマイナスなイメージだからです。
部署を存続させるため、1番必要なのは「人」「人材」です。
働く人たちがいないと、経営は成り立ちません。
そして働く人たち(つまり所属のケアマネ)が、自ら職場を存続させたいと感じることが理想です。
そこに必要なのは「ノルマ」ではなく、「目標」。
スタッフが自主的に「頑張りたい」と思うように整えるのが、管理者の役割なわけです。
ちなみに管理職時代には、私はスタッフとの関わり方で、こんなことを意識していました。
【居宅ケアマネの「ノルマ」を「目標」に変えたい!】
- 現在の収益や不足を数値化し、あと何件担当すれば改善されるか「見える化」
- 残業になるなら、困っていること・改善策・周囲でフォロー可能なことを一緒に考える
- 担当人数を増やすことは、地域に必要とされる存在になるとスタッフに伝える
新人ケアマネ時代は、イヤだった「ノルマ」。
でも管理者になると、その必要性もわかりました。
じゃあ前向きに考えるなら・・・ということで、「目標」。
これで私自身の意識も大きく変わったのです。
【居宅ケアマネのノルマ】ヒラのケアマネの立場
そして今の職場では、私はイチ従業員(ヒラのケアマネ)として勤務をしています。
意識しているのは、ただノルマを課せられ「やらされている仕事」にしないこと。
それは自分自身の安定した生活や、心身の健康状態を保つためです。
いかに、鮮やかにノルマを達成するか。
戦略を立てて意見をしたり、スケジュール管理の工夫で残業を回避しています。
仕事にメリハリがついて楽しいし、評価も上がって一石二鳥。
定時に帰れて、お給料が上がる可能性だってあるのです。


そして今まさに、法人トップから「全員担当人数を○○人にすること!」とノルマが課せられています。
そこで私は管理者と面談し、「どう考えているのか、本当に必要なノルマなのか」を問いました。
管理者は、ケアマネ部署を存続するためには、ノルマが必要という考えです。
でも・・・。


みんなが残業になることも心配で・・・
板挟みになって悩んでいました。
ちなみに私は、このノルマは達成できるイメージがありました。
- 新規利用者を増やすためには、どうしたら良いのか。
- スタッフみんなが自主的に「ノルマを達成しよう」となるには、どう意識づけるのか。
こんなことを管理者と一緒に考えたのです。
これは、私が新人ケアマネだった頃は、思いもつかなかったことです。
現在の私にとっては、ノルマは「目標」です。
それでモチベーションが上がり、行動が変化したのでした。
【まとめ】 居宅ケアマネのノルマがなくならない理由を解説!
現実として、居宅ケアマネの職場ではノルマはあります。
ノルマと呼んでいなくても、言葉や形を変えたノルマが課せられているのです。
それは、居宅介護支援事業所の経営上は、ある程度仕方ないです。
でもだからこそ、経営者や管理者の方針を知り、それに共感して「ノルマ」を「目標」に変えたいものです。
ただの雇われではなく、「自分がこの部署の主役だ!」と思って働いた方が楽しいですよね。
でも現場を無視して数字だけで判断し、理不尽なノルマを課してくる上司もいるかもしれません。
自分のキャパ以上の仕事を与えられるのはとても辛いものです。
そんな時は、転職を考えましょう。
- ケアマネの仕事をよく理解している経営者
- スタッフをよく見ていて守ってくれる管理者
そんな職場に出会えるはずです。


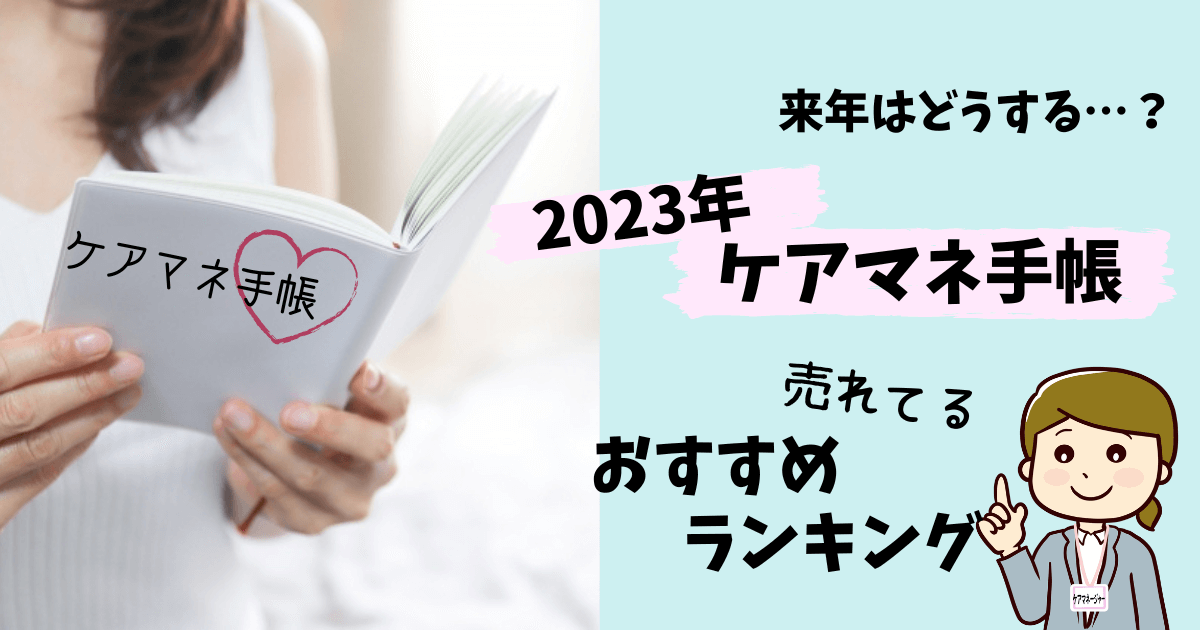
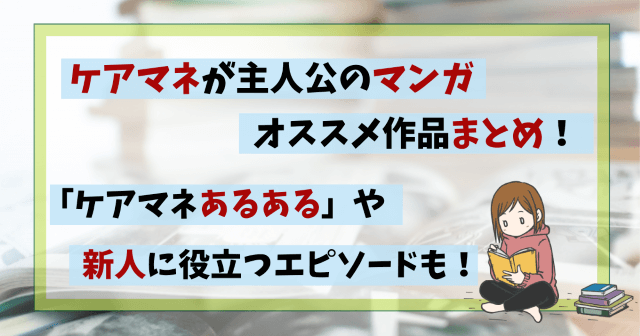


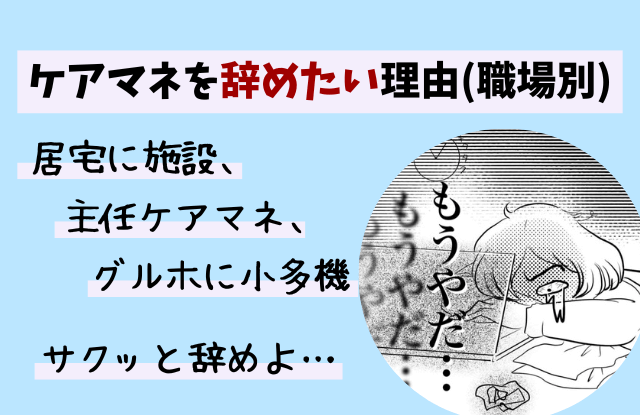
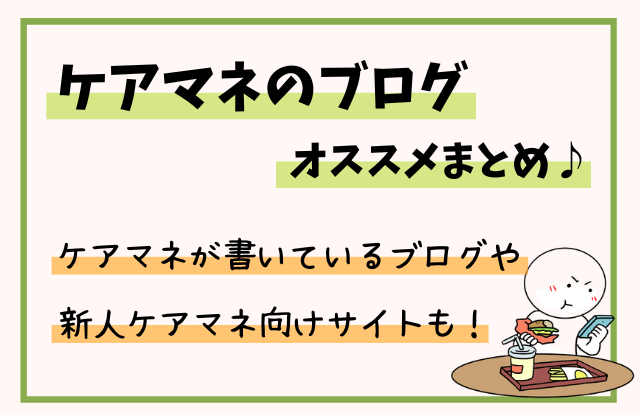
コメント